自己決定理論とは
子どもたちの成長を見守る中で、私は「自己決定理論」が家庭教育においても非常に役立つと感じています。自己決定理論とは、人が自分の行動を内発的な動機づけ(自分の意思で行動する力)によって選び、成長していく心理学の理論です。この理論には「自律性(=自分で決める力)」「有能感(=できた!という自信)」「関係性(=信頼してつながる安心感)」という3つの基本的な欲求があり、これらが満たされることで人は前向きに物事に取り組むことができます。
今回は、小学二年生の息子と年少の娘、それぞれのエピソードを通じて、自己決定理論をどう活かしているかをお話しします。
息子の「自律性」を引き出す家庭学習

息子は学校が好きで、勉強に対しても積極的です。ただ、「親から言われたからやる」というスタンスではなく、「自分で決めて取り組む」という自律性を育てることが重要だと考えました。
例えば、家庭学習の計画を立てるとき。「今日はこれをやって」とこちらが一方的に決めるのではなく、息子自身に選択肢を与えました。「今日は漢字練習と読解問題、どちらからやりたい?」と聞くことで、彼自身が学習の流れをコントロールできます。初めのうちは自分が得意な計算問題を選びがちでした。それも結局読解問題にも取り組むので、気づいた時には「面倒なものは先に終わらせてしまおう」スタイルに変わり、いまでは読解→漢字→文章題→計算問題という流れがほぼ固定化しています。生活リズムが少し乱れたときにも、「明日は早く起きて登校前にやっちゃいたい」と自分で軌道修正もするようになりました。
ここで大切なのは、親が提案した選択肢に対して「いいね、そうしよう」と肯定することなんだそうです。ついつい口を出したくなりますが、ぐっと我慢。子どもが自分の決定を尊重されることで、内発的なやる気が引き出されます。
年少の娘との遊びを通じた「有能感」の育成

一方、年少の娘は遊びが中心の生活ですが、自己決定理論の「有能感」を意識することが、日々の関わりで役立っています。ある日、娘がブロック遊びで大きなタワーを作っていました。途中で崩れてしまったとき、「もう~~~!!」と投げ出しそうになった娘に、「ちょっと工夫してみたらどう?」と声をかけました。
「工夫する」という提案自体が、娘にとっては新しい視点でした。どういうこと??と聞かれたのですが、少しずつヒントを出して、結果として「もっと下を広くしてみる!」と自分で気づき、最初作っていたものよりも高いタワーを完成させたとき、娘の顔は自信に満ちていました。「できた!」という達成感は、次の挑戦へのモチベーションにつながります。
このような小さな成功体験を積み重ねることで、子どもは「自分はできる」という感覚を育んでいきます。
親子の「関係性」を深めるコミュニケーション
自己決定理論の3つ目の要素である「関係性」は、親子のつながりを強めるポイントです。我が家では、どんなに忙しくても子どもたちと向き合う時間を意識的に作っています。例えば、息子が「今日のテストでミスっちゃって~」と話したときは、「どんな問題だったの?」と興味を持って聞きます。彼が自分のケアレスミスや失敗を共有してくれることが、親子の信頼関係を深めるきっかけになります。
また、年少の娘には、遊びや日々の出来事を共有する時間を大切にしています。たとえブロック遊びやおままごとといった日常的なことでも、「楽しいね」「上手にできたね」と共感することで、安心感やつながりを育てています。できるだけわざとらしくないように、本当に共感できているように、目線を合わせてにこっと笑うことを意識しています。
自己決定理論を日常に生かすコツ
自己決定理論を家庭で取り入れるには、「親がすべてをコントロールしないこと」が大切だと感じます。子どもが自分で決め、行動し、成功や失敗を経験する過程を、親が優しくサポートする姿勢が求められます。
実際、息子が家庭学習の時間を「朝にする」と決めたときも、最初は親の私が「朝はバタバタするなぁ…帰宅後のほうが落ち着いて時間が取りやすいのでは?」と思っていました。しかし、彼の選択を尊重してみると、朝のほうが集中できることがわかりました。子どもが自分の意思で行動することで得られる自信は、想像以上に大きいものです。
まとめ
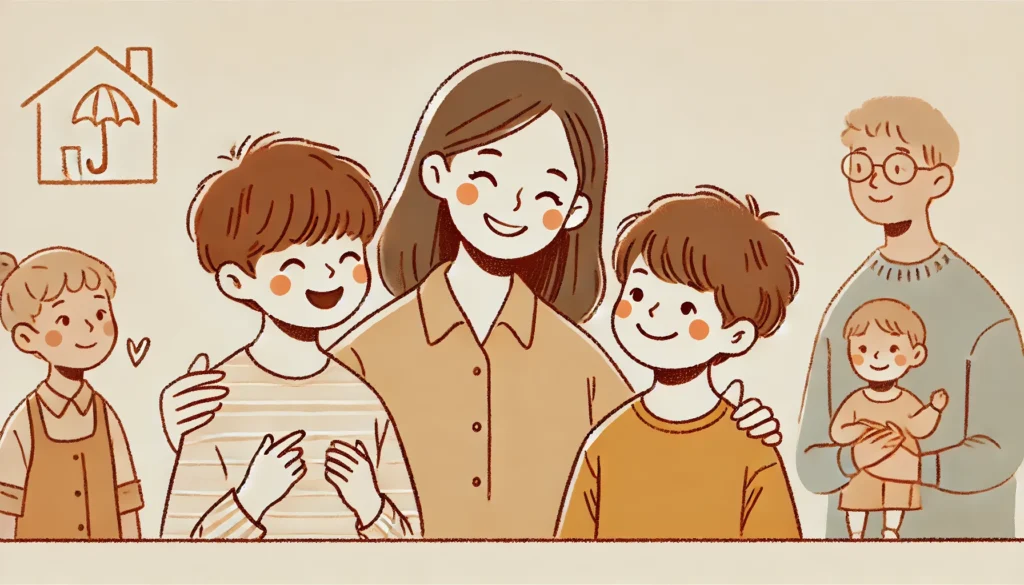
自己決定理論を意識した家庭教育は、子どもたちの成長に大きな力を与えます。「自分で選ぶ」「自分でできた」と感じられる環境を整えることで、子どもは内発的なやる気を持って学びや遊びに取り組むようになります。
日々の生活の中で、子どもが決めた小さな選択を尊重し、成功体験を積み重ねること。それが、子どもの自己肯定感を高め、主体的に生きる力を育む第一歩だと思います。

