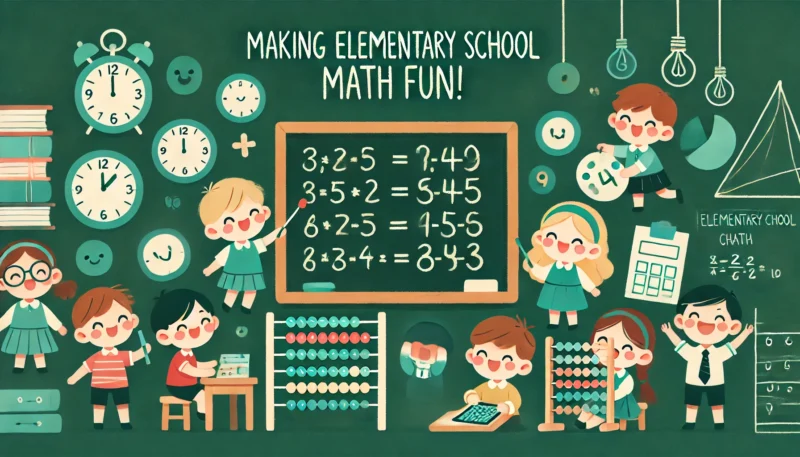こんにちは!我が家には、小学二年生の息子と幼稚園年少の娘がいます。息子は学校が大好きで、特に算数が得意。毎日のように「ママ、今日の宿題面白かったよ!」と目を輝かせて話してくれます。一方、娘はまだ幼稚園生ですが、お友だちと一緒にブロックで遊んだり、数を数えたりするのが大好き。そんな子どもたちの様子を見ていると、「算数を楽しむ気持ちって、どうやって育つんだろう?」と考えることがよくあります。
実は、算数が苦手な子でも、ちょっとした工夫で「楽しい!」と思える瞬間を作れるんです。今回は、児童発達心理学の視点も交えながら、小学生の計算や図形が好きになる家庭での学び方をご紹介します。SEO対策も意識して、「算数 楽しい 学び方」「小学生 算数 苦手 克服」といったキーワードで検索するパパママに届くよう工夫しました。それでは、さっそく始めましょう!
1. 算数が苦手な子どもの気持ちを理解する
まずは、子どもが「算数が苦手」と感じる理由を考えてみましょう。小学二年生くらいになると、足し算や引き算に加えて、繰り上がりや繰り下がり、簡単な図形の問題が出てきますよね。このタイミングでつまずく子も少なくありません。児童発達心理学では、「具体的なものから抽象的なものへの移行」がこの年齢の大きな課題と言われています。つまり、手で触れるブロックやお菓子なら簡単に数えられるのに、紙の上の「記号」や「数字」になるとピンとこない子が多いのです。
我が家の息子も、最初は繰り上がりの計算で「えー、どういうこと?」と首をかしげていました。友達のママに聞いてみると、「うちの子、図形の面積とか聞くと『何!?』って固まっちゃう」と笑っていました。SNSでも「算数の宿題で泣き出す我が子…助けて!」なんて投稿をよく見かけますよね。子どもにとって、算数が「わからない=楽しくない」になってしまうのは自然なこと。だからこそ、親が「楽しい!」と思えるきっかけを作ってあげることが大事です。
2. 計算をゲームに変える!家庭でできるアイデア
では、どうやって算数を楽しくするか?まずは「計算」を取り上げてみましょう。計算って、単純作業に感じると途端に飽きちゃいますよね。そこで、我が家で試してみて大成功だった方法を3つ紹介します。
(1) お菓子で足し算・引き算
息子が繰り上がりを練習していたとき、「数字だけじゃつまんない!」と言い出したことがありました。そこで、キッチンからクッキーを10枚持ってきて、「これをママと分けてみよう」と提案。5枚ずつ分けた後、「ママが2枚食べちゃったら残りは何枚?」と聞いてみると、「えっと…3!」とニコニコで答えてくれました。お菓子を使うと、「数」がリアルに感じられて計算が身近になるんです。
児童発達心理学でも、「具体物を使った学び」は脳の発達に効果的とされています。数を「見える形」にすることで、頭の中でイメージしやすくなるのです。「おはじきで計算したら子どもが楽しそうだった!」という声もあります。お菓子やおはじき、積み木などなど家にあるもので気軽に試してみてください。
(2) 買い物ゲームで実践練習
週末のスーパーでの買い物も、算数のチャンス!我が家では「200円まででお菓子を選んでね」と息子にミッションを出します。例えば、50円のグミと80円のチョコを選んだら、「これ、合計いくら?」と聞いてみる。自分で計算して「130円!まだ70円余るね!」と気づく瞬間が楽しそうなんです。
実際の買い物の際は切りのいい数字でないことが多いので、我が家の場合は1年生のうちは一の位は切捨てにするなどしていました。
この日常生活の中で「算数を使っている!」と実感することがポイントなのだと思います。小学生くらいの子は「自分ごと」にするとぐっと興味が湧きます。少量の買い物ときにはレジより早く合計を計算できるかと、ゲーム感覚で計算をさせることもよくあります。
(3) タイムアタックで競争心を刺激
息子が「もっとやりたい!」と言ったのは、計算のタイムアタック。100マスの足し算シートを用意して、「何分でできるかな?」とストップウォッチを手に持つと、俄然やる気が出たようです。就学前に初めてチャレンジしたときは5分以上かかっていたものが、今では2分を切りました。「次は1分目指す!」と意気込んでいます。
心理学的に見ても、「達成感」は子どものやる気を引き出す鍵といいます。ゲーム感覚で「できた!」を増やすと、苦手意識が薄れていきます。ほかにも、スキマ時間にアプリで計算ゲームさせてみるのもいいと思います。無料のアプリもたくさんあるので、試してみるのもおすすめです。
3. 図形を「遊ぶ」感覚で好きになる工夫
次は「図形」です。面積や角度って、小学生にはちょっと難しいですよね。でも、図形って実は「遊び」に変えやすいんです。我が家が活用しているアイデアを紹介します。
(1) 折り紙で図形パズル
息子が平行四辺形のものを見せて「これって三角形?」と聞いてきたとき、折り紙を出して「これを半分にしてみて」と一緒に折ってみました。できた三角形を見て、「角が3つあるね、これが三角形だよ。そっちは角がいくつある?」と聞いてみると、平行四辺形は4つ角があることに気がづき「三角形じゃないねぇ」と言っていました。娘も幼稚園で折り紙が好きなので、一緒に「正方形できた!」と盛り上がります。
手で触って形を作る経験は、図形の理解を深める近道です。児童発達心理学でも、「身体を使った学び」が空間認識能力を育てると言われています。
(2) お絵かきで面積をイメージ
面積が苦手な子には、お絵かきがおすすめ。方眼紙に「ママの家と息子の家、どっちが広いかな?」と聞いて、好きな形の家を描いてもらいます。マス目を数えて「ママの家は10マス、息子のは15マスだから広いね!」と比較すると、「面積ってこういうことか!」と納得した顔に。
視覚的に捉えることで抽象的な概念が具体的になります。身近なもので試せるのがいいですよね。
(3) 宝探しで空間感覚を磨く
図形の楽しさを味わうなら、宝探しゲームも最高です。我が家では、リビングに「お菓子を隠したよ。ヒントは『ソファの右、テーブルの左』だよ」などと伝えると、娘が「右ってどっち!?」と動き回りながら探します。空間を意識する遊びは、図形問題で大事な「位置関係」を自然に覚えるきっかけになります。
他にも、家の間取り図を描かせてみたり、立体的なパズルをいろいろな方角から見て紙に書いてみるなどもおすすめです。遊びながら学べるなんて、親としても嬉しいですよね。
4. 親の関わり方で「好き」を育てるコツ
最後に、親としてどう関わるかも大事なポイントです。子どもが「算数が楽しい!」と思うには、親のリアクションが大きな影響を与えると思っています。心理学でも、「他者からの承認」が子どもの自信につながるとされています。
(1) 「できた!」を一緒に喜ぶ
息子が宿題を終えたとき、「すごいね!こんな難しい問題できたんだ!」と大げさに褒めると、照れながらも嬉しそう。逆に、「まだ間違ってるよ」と指摘ばかりだと、モチベーションが下がってしまいます。「できたこと」にフォーカスして褒めるのがコツです。
(2) 失敗しても「次があるよ」と応援
計算ミスや図形の書き間違いがあっても、「大丈夫、次やってみよう!」と励ますと、息子も「うん、また頑張る!」と前向きに。失敗を恐れず挑戦する気持ちが、算数を好きにさせる土台になります。
(3) 一緒に楽しむ姿勢を見せる
私も「ママ、面積って忘れちゃったな。一緒にやってみよう?」と息子に教えてもらうことがあります。すると、「ママ、ここはこうだよ!」と得意げに説明してくれます。親子で学ぶ楽しさを共有すると、子どもも「算数って面白い!」と感じやすいですよ。
5. まとめ:算数は「楽しい!」が一番の近道
我が家の息子を見ていると、算数が好きになる秘訣は「楽しい!」と感じる瞬間を増やすことだと実感します。計算をお菓子やゲームで遊んで、図形を折り紙やお絵かきで身近に。親が一緒に楽しむ姿勢を見せれば、子どもも自然と「もっとやってみたい!」と思うはず。
「小学生 算数 苦手 克服」や「算数 楽しい 学び方」で検索してここにたどり着いたパパママ、ぜひ今日から一つ試してみてください。子どもが「算数って面白い!」と笑顔になる瞬間を、一緒に見届けましょう!我が家もこれからも、子どもたちと一緒に学びながら、楽しいエピソードを増やしていきたいと思います。