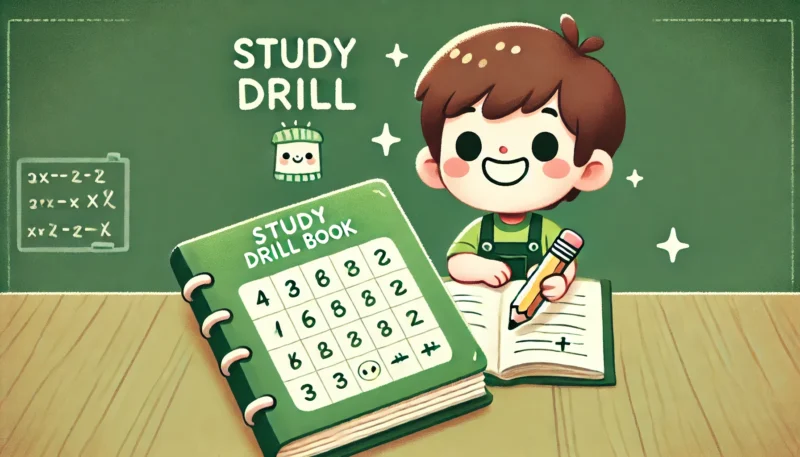お子さんの学習習慣を確立し、苦手を克服する方法のひとつに「ドリル学習」があります。ドリルは短時間で取り組めるため、集中力を保ちやすく、基礎力を効率的に強化できる優れた学習ツールです。しかし、どのように選び、活用すれば効果的なのか迷われる保護者の方も多いのではないでしょうか。本記事では、ドリル学習のメリットと選び方、活用方法について詳しく解説します。
1. ドリル学習のメリット
1-1. 学習習慣を身につけやすい
ドリルには様々のものがありますが、1ページあたりの問題数が少なく、1回の学習時間を短く区切れるものが多くあります。そのため、子どもが飽きにくいというメリットがあります。「毎日1ページ」と決めて取り組むことで、学習習慣を自然に身につけることができます。
1-2. 苦手分野の発見と克服ができる
学習を進めていく中で、スムーズに解ける問題とつまずく問題が明確になります。家庭学習でドリルを活用すると、子どもが苦手な分野を早い段階で発見でき、その部分に重点的に取り組むことで効率的な克服が可能になります。
1-3. 書店で中身を確認できる
ドリルの大きな利点は、書店で実際に中身を見て選べることです。子どもの学力や興味に合ったものを選ぶことができ、無駄なく学習を進めることができます。
1-4. 価格が手頃で続けやすい
市販のドリルは1冊1,000円前後で購入できるものが多く、長期間にわたって継続しやすい価格設定になっています。家庭学習を手軽に始められるのも大きな魅力です。
1-5. 達成感が得られやすい
ドリルは見開きや1ページで完結することが多いため、子どもが「できた!」という達成感を味わいやすい教材です。また、シールが付属しているものもありますし、キャラクターを起用しているものもあります。ポジティブな要素が詰め込まれているドリルなら、達成感を感じやすくその達成感がモチベーションとなり、学習を継続しやすくなります。
2. 子どもに合ったドリルの選び方
2-1. 現在の学力に合ったレベルのものを選ぶ
ドリルを選ぶ際は、子どもが「少し頑張ればできる」レベルのものを選びましょう。難しすぎると挫折しやすく、簡単すぎると学習効果が薄れます。
2-2. 苦手分野に特化したドリルを選ぶ
苦手分野の克服を目的とする場合には、その分野に特化したドリルを選ぶと効果的です。例えば、計算が苦手な場合は「くり上がり・くり下がりに特化したドリル」などを選ぶと、効率的に力をつけられます。
2-3. 興味を引くデザインのものを選ぶ
子どもが興味を持ちやすいキャラクターが描かれているものや、カラフルなデザインのものは、学習への意欲を高めるのに役立ちます。
2-4. 解説が充実しているものを選ぶ
ドリルの中には、解答だけでなく、解説が丁寧に記載されているものもあります。保護者がサポートしやすく、子どもが理解を深めやすくなります。
3. ドリル学習の効果を最大化する方法
3-1. 学習時間を固定する
「毎朝7時から10分間」「学校から帰ったらすぐ」など、学習時間を固定すると、習慣として定着しやすくなります。
3-2. ご褒美システムを取り入れる
「5ページ終えたらシールを貼る」「10ページ終わったら好きな本を買う」など、小さな目標を設定し、ご褒美を用意することで、学習意欲を高めることができます。
3-3. 保護者が適度にサポートする
ドリル学習は基本的に自学自習ができる教材ですが、保護者がサポートすることで、子どもがつまずくポイントをスムーズに解決できます。やりっぱなしでは身につきませんので、ここは最後の丸付けだけでも保護者が時間を取ることが望ましいです。
3-4. 1冊終えたら振り返りをする
ドリルを1冊終えたら、間違えた問題を見直し、どれくらい成長したかを確認しましょう。復習することで、より確実に知識を定着させることができます。また、やり切ったドリルもすぐに捨てず、邪魔にならないようであれば、ためておくことをお勧めします。途中途中で振り返り、「あなたはこんなにがんばってきたんだよ!すごいよ!」と褒めてあげましょう。
まとめ
ドリル学習は、手軽に取り組める上に、苦手克服や学習習慣の定着に大きな効果をもたらします。書店で実際に中身を確認しながら子どもに合ったものを選ぶことで、より効果的に活用できます。お子さんの学習をサポートするために、ぜひドリル学習を取り入れてみてください。