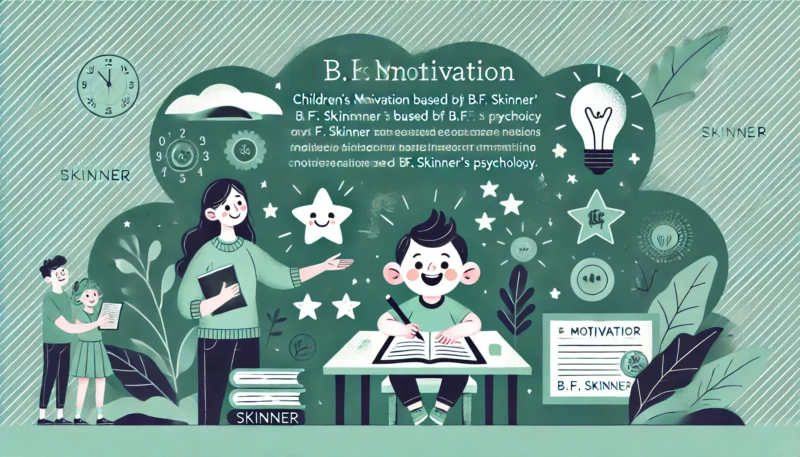【心理学で考える子どものやる気】報酬の影響と上手な使い方
子どもが勉強や習い事を頑張るために「ご褒美」を使うのは、親としてよくある工夫のひとつです。しかし、「ご褒美をあげすぎると、やる気がなくなる」と聞いたことはありませんか?
実は、心理学者B.F.スキナーの「オペラント条件付け」という理論によると、報酬(ご褒美)は行動を強化する効果があります。ただし、その使い方を間違えると、かえって子どもの内発的動機づけ(自発的にやる気を持つこと)を損なってしまう可能性があるのです。
今回は、スキナーの心理学をもとに「報酬の影響」と「ご褒美の上手な使い方」について、小学生の子どもを持つ親が実践しやすい具体例を交えて解説します。
1. スキナーの「報酬の影響」とは?
スキナーは、オペラント条件付けという理論を提唱しました。この理論では、行動の結果として報酬(正の強化)が与えられると、その行動が強化され、今後も続く可能性が高くなるとされています。
たとえば、
- 子どもが宿題を終えたらシールを貼る → 宿題をする習慣がつく
- 掃除を頑張ったらお菓子をあげる → 掃除をする頻度が増える
このように、ポジティブな報酬を与えることで、特定の行動を促すことができます。しかし、一方で報酬を与えすぎると、「報酬がないとやる気が出ない」という状態になってしまうことも。これが、内発的動機づけの低下につながるのです。
2. ご褒美が逆効果になる理由
一見、報酬を与えることは良いことのように思えますが、注意が必要です。特に「外発的動機づけ」(外からのご褒美が目的で行動すること)が強くなりすぎると、子どもは「ご褒美がもらえないならやらない」と考えてしまうようになります。
例えば、
- 「100点を取ったらゲームを買ってあげる」と約束する → ゲームが目的になり、勉強自体を楽しめなくなる
- 「本を読んだらお小遣いをあげる」とする → お小遣いがないと読書をしなくなる
このように、行動の理由が「ご褒美のため」になってしまうと、ご褒美がなくなった瞬間にやる気もなくなってしまいます。
3. 内発的動機づけを損なわないご褒美の使い方
では、どのように報酬を使えばよいのでしょうか?
ポイントは、
- 物質的なご褒美を減らす(シールやお菓子などの外的報酬を使いすぎない)
- 褒め言葉や達成感を報酬にする(子ども自身が「できた!」と思える経験を増やす)
- ご褒美の頻度を調整する(毎回でなく、予測できないタイミングで与える)
具体的な実践例を見てみましょう。
【実践例①】 宿題を習慣化させる
NG例:宿題をしたら毎回お菓子をあげる → お菓子が目的になり、宿題が嫌いになる
OK例:「宿題終わったんだね!えらいね!」と声をかける + 「頑張ったから今日は好きな本を一緒に読もうか」と親子の時間を作る → 達成感と楽しみがセットになり、宿題の習慣がつく
【実践例②】 自主的に読書をさせる
NG例:1冊読んだら100円のお小遣いをあげる → お金が目的になり、読書を楽しめなくなる
OK例:「この本面白そうだね!読んだらどんなお話か教えて!」と子どもの話を聞く + 「それはすごいね!」と感想を伝える → 親と共有することが楽しくなり、自然と本を読むようになる
【実践例③】 スポーツや習い事のモチベーションを上げる
NG例:試合で勝ったら高額なおもちゃを買う → 物が目的になり、努力する意味が変わる
OK例:「練習頑張ったね!」と努力自体を褒める + 「今日のプレーすごく良かったね!」とプロセスに注目する → 勝ち負けよりも成長を実感できるようになる
4. まとめ:ご褒美は「形」より「気持ち」が大切
スキナーの理論によれば、報酬は子どもの行動を強化する効果があります。しかし、報酬の使い方を間違えると、子どもが「ご褒美がないとやらない」状態になってしまいます。
そのため、
- 物質的なご褒美を控えめにする
- 褒めることや達成感を報酬にする
- ご褒美のタイミングを工夫する
この3つを意識しながら、日々の子育てに取り入れてみてください。少しの金銭で買えるお菓子やおもちゃはとても手軽に与えられるご褒美ですがもろばのを意識しながら、日々の子育てに取り入れてみてください。少しの金銭で買えるお菓子やおもちゃはとても手軽に与えられるご褒美ですが取り入れ方には工夫が必要ですね。子どもが「やらされている」ではなく「自分からやりたい!」と思える環境を作ることで、長い目で見た学習意欲や成長につながっていくはずです。一緒に頑張りましょう!