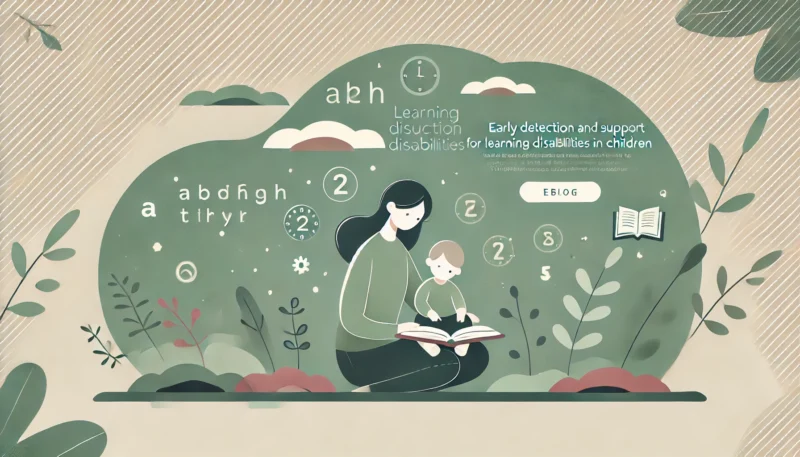親子で机に向かう家庭学習のタイミングは子どもとじっくり向き合う絶好の機会です。心に余裕のある時には親子で楽しみながら学ぶ時間を持つことができる一方で、「もしかしてうちの子、他の子とちょっと違う?」と気づく瞬間もあるかもしれません。
実際、学習障害(LD)や発達障害(ADHD・ASDなど)は、幼少期からサインが見られることが多いですが、気づかれないまま成長するケースも少なくありません。そこで今回は、学習面や発達面での心配なサインと、それにどう対応すればよいかについて、親しみやすく分かりやすく解説します。
1. 学習障害(LD)とは?
学習障害(LD)は、知的発達には問題がないものの、「読む・書く・計算する」などの特定の学習分野に困難が生じる障害です。
LDの主な特徴
- ひらがなを覚えるのに時間がかかる
- 読み書きに苦手意識が強い
- 計算ミスが多い(繰り上がり・繰り下がりの理解が難しい)
- 黒板の文字を書き写すのに時間がかかる
「勉強が苦手なのかな?」と見過ごされがちですが、実は脳の働き方の違いが影響している可能性もあります。
実際のエピソード:ひらがなが苦手なA君
A君(小学2年生)は、数字の計算は得意なのに、ひらがなを書くのがとても苦手でした。お母さんは「ただの苦手意識かな?」と思っていましたが、小学校の先生から「文字の鏡文字が多い」と指摘されました。専門機関で相談すると「識字障害(ディスレクシア)の可能性がある」とのこと。そこからは音読をアプリで練習したり、タブレット学習を取り入れたりして、少しずつ克服していきました。
2. 発達障害(ADHD・ASD)とは?
発達障害にはさまざまな種類がありますが、特に小学生によく見られるのが「ADHD(注意欠陥・多動性障害)」と「ASD(自閉スペクトラム症)」です。
ADHDの主な特徴
- 落ち着きがなく、授業中に立ち歩いてしまう
- 忘れ物が多い、持ち物を管理するのが苦手
- 話の途中で割り込んでしまう
- 宿題や課題に集中できず、途中で投げ出すことが多い
ASDの主な特徴
- こだわりが強く、いつものルールを崩されるとパニックになる
- コミュニケーションが苦手で、友達と上手く遊べない
- 感覚過敏があり、大きな音や特定の触感を嫌がる
- 表情やジェスチャーを読み取るのが難しい
実際のエピソード:忘れ物が多いB君
B君(小学1年生)は、学校に行く準備をしても必ず何かを忘れてしまうタイプでした。お母さんは「性格の問題かな?」と思っていましたが、先生から「ワーキングメモリが弱いかもしれませんね」と言われ、発達検査を受けることに。結果、軽度のADHD傾向があり、チェックリストを活用して準備をサポートすることで、忘れ物が少なくなっていきました。
3. 早期発見のためにできること
「うちの子、大丈夫かな?」と少しでも気になったら、以下の方法で様子を確認してみましょう。
(1) チェックリストを活用する
以下のような簡単なリストを作り、気になる行動がないか振り返るのも一つの方法です。
| 項目 | 頻度(ほぼ毎日/たまに/ない) |
|---|---|
| 文字を書くのが極端に遅い | |
| 計算ミスが目立つ | |
| 落ち着きがなく、すぐに立ち歩く | |
| 友達とうまく遊べない |
(2) 先生や専門家に相談する
学校の先生やスクールカウンセラー、発達相談センターなどに相談すると、専門的なアドバイスをもらえます。
(3) 家庭でできる対応策
- 学習サポート:タブレット学習や音読アプリを活用する
- 環境調整:勉強する場所をシンプルにして集中しやすくする
- ルールの見直し:持ち物リストや時間割を目に見える場所に貼る
4. まとめ
学習障害や発達障害の特徴は子どもによってさまざまですが、「ただの苦手」ではなく「特性」として理解することが大切です。春休みは、お子さんの得意・不得意を見つめ直すチャンス。気になる点があれば、専門家に相談しながら、家庭でできるサポートを取り入れてみましょう。
どんな特性を持っていても、お子さんが自分らしく成長できるよう、親としてできることを一緒に考えていきましょう!