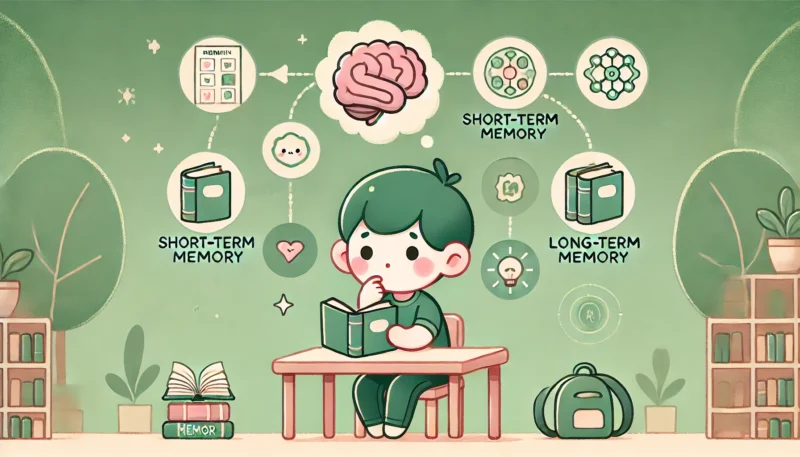記憶の二重貯蔵モデルとは?
私たちが日々の生活で得た情報を記憶する仕組みには、心理学者アトキンソンとシフリンが提唱した「記憶の二重貯蔵モデル」があります。このモデルによると、記憶は「短期記憶」と「長期記憶」の二つのシステムによって成り立っています。
短期記憶は、一時的に情報を保持するシステムで、数秒から数十秒程度の間しか情報を記憶できません。一方で、長期記憶は、一度定着すると何年にもわたって保持される記憶のことを指します。では、どのように短期記憶を長期記憶へと移行させることができるのでしょうか?
短期記憶から長期記憶への移行には「繰り返し」と「深い理解」が鍵
アトキンソン&シフリンのモデルでは、短期記憶から長期記憶へと情報を定着させるためには「繰り返し」と「深い理解」が必要であるとされています。
① 繰り返し(リハーサル)の重要性
短期記憶は、一度に保持できる容量が限られています。研究によると、成人の短期記憶の容量は「7±2個の情報」とされており、子どもの場合はさらに少ないことが分かっています。そのため、記憶を長期的に保持するためには、何度も情報を繰り返し思い出し、定着させる必要があります。
例えば、九九の暗記を考えてみましょう。子どもは九九を一度聞いただけでは覚えられませんが、毎日繰り返し練習することで、やがて長期記憶として定着します。このように「反復練習」が記憶の定着に欠かせないのです。
② 深い理解を促す学習法
単なる暗記ではなく、「なぜそうなるのか?」を考えることで、情報がより深く記憶に残ります。これを「意味的処理」と言います。
例えば、算数の文章題を解く際、子どもが「足し算と引き算のどちらを使えばいいのか?」を考える場面があります。ただ計算方法を暗記するのではなく、「なぜ足し算なのか?」を理解することで、より深い学習が可能になります。大人が子どもに対して「なぜそう思うの?」と問いかけることで、思考力を育みながら記憶の定着を助けることができます。
記憶の二重貯蔵モデルを活用した学習方法
この心理学モデルを日常の学習に取り入れることで、子どもの学びをより効果的にサポートできます。
1. 反復練習を習慣化する
子どもの学習では、定期的な復習が重要です。例えば、漢字や英単語を覚える際、一度学んで終わりではなく、翌日・1週間後・1か月後に繰り返し復習することで長期記憶へと移行しやすくなります。
2. 「なぜ?」を問いかける
子どもが学んだことに対して、「どうしてそうなるの?」と質問を投げかけることで、表面的な暗記ではなく、概念を理解しながら学ぶ姿勢が身につきます。
3. 視覚や体験を活用する
情報を単に聞くだけでなく、目で見たり体験したりすると記憶に残りやすくなります。例えば、算数の「長さ」を学ぶときに実際にメジャーで測ってみたり、理科の実験を通じて学ぶことで、深い理解と長期記憶への定着が促されます。
まとめ
記憶の二重貯蔵モデルは、短期記憶と長期記憶の関係を示した重要な理論です。短期記憶から長期記憶へ移行させるには、「繰り返し」と「深い理解」が必要不可欠です。学習においては、反復練習を習慣化し、「なぜ?」と考えさせる問いかけをすることで、子どもの記憶定着を効果的に促すことができます。
日々の学習にこの心理学の視点を取り入れながら、子どもが楽しく、確実に知識を身につけられる環境を整えていきましょう。